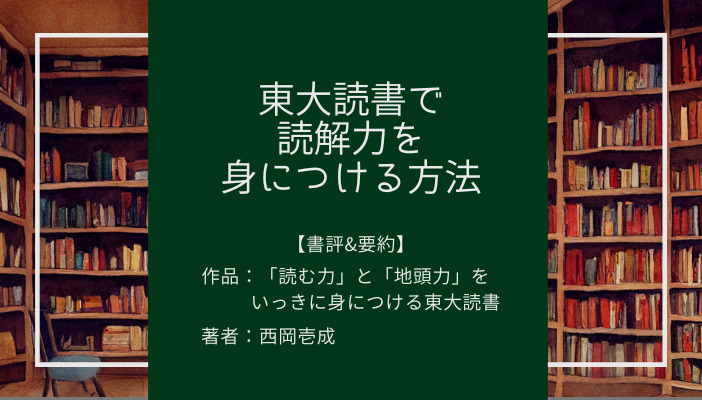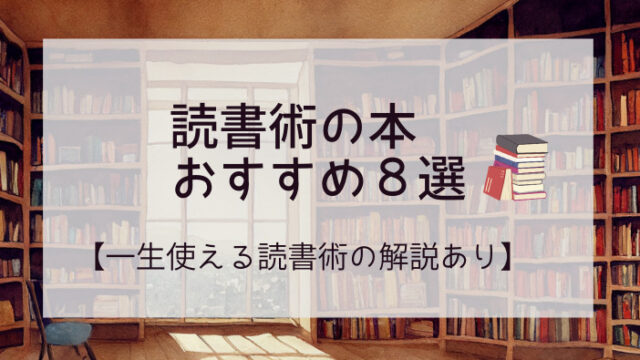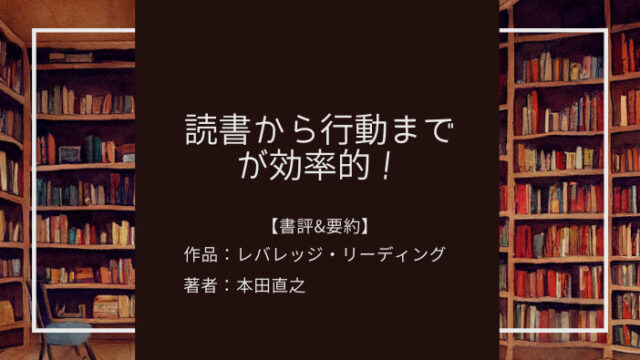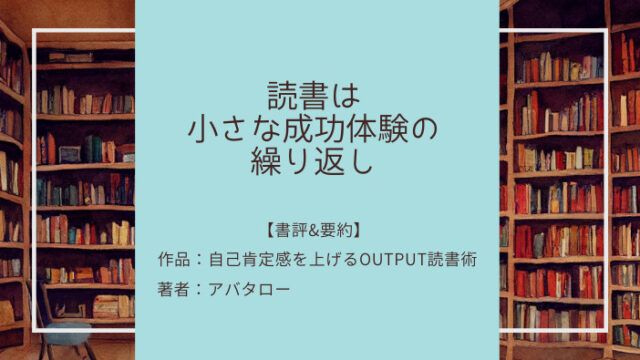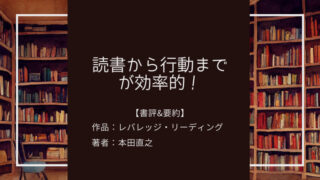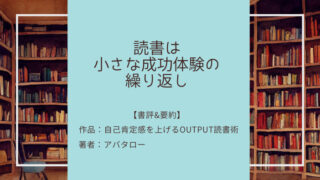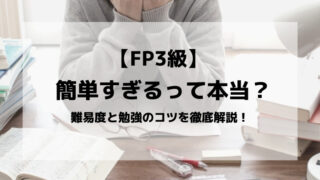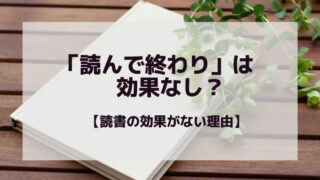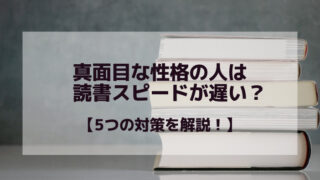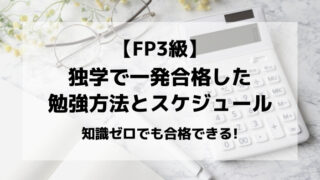「読解力を身につけたくて読書を始めたけど、ちゃんと理解できているのかわからない」
このように思うと、読書を習慣化したくても続きませんよね。
私も長年読書に苦手意識があったので、いざ読書をしてみても自信を持てませんでした。
そんな悩みのヒントをくれたのが、今回ご紹介する『東大読書』です!
読書が苦手だった私でも、本を理解するコツをつかむことができました。
本記事では、『東大読書』で身につけられる力のうち、「読解力」に焦点をあてて解説します。
読書術のおすすめ本を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
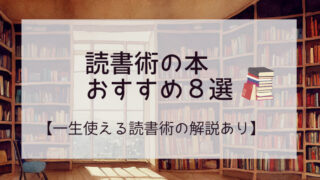
『東大読書』はどんな本?
- 作品名:「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書
- 著者:西岡壱成
- 出版:東洋経済新報社(2018/6/1)
- 頁数:282ページ
こんな人にオススメ
- 読書で「読解力」を身につけたい
- 本を読んでもいまいち理解できない
- 読書で「考える力」を身につけたい
著者情報
- 執筆当時、現役東大3年生
- 学内書評誌「ひろば」の編集長
- 人気漫画『ドラゴン桜2』に情報提供する東大生団体のリーダー
- 『「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく 東大思考』
- 『書き込み式「東大作文練習ノート」つき 東大作文』
- 『「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる 東大作文』
著者の西岡氏はもともと頭が良かったわけではなく、高校時代偏差値35から2浪のすえ、見事合格できたという経歴をお持ちです。
東大に合格できたキッカケは「本の読み方」を変えたこと。
受動的ではなく能動的に読むことで、地頭力は良くなるといいます。
能動的に読むとは「本と徹底的に議論する読書」。つまり、東大読書は本と会話する読書といえます。
偏差値35から這い上がった著者だからこそ、初心者にもわかりやすく1つ1つ丁寧に解説されています!
『東大読書』で身につく力
西岡氏は、本の読み方を変えれば誰でも「読む力」と「地頭力」が身につくといいます。具体的には次の5つの力です。
①読解力;文章を読み込んで理解する力
②論理的思考力:論理の流れがクリアに追える力
③要約力:人に説明できるように情報をまとめる力
④客観的思考力:多面的なモノの見方をもつ力
⑤応用力:得た知識を活かせるようにする力
本書はPART1、PART2にわかれており、1で読書法の解説、2で選書方法の解説という構成になっています。
PART1の「読書法」は5つのステップにわたり、各ステップごとに上記の力を身につける方法が解説されています。
本記事では、ステップ2「取材読み」、ステップ3「整理読み」の項目から、私が特に参考になったポイントを解説していきますね。
『東大読書』から学んだことと要約
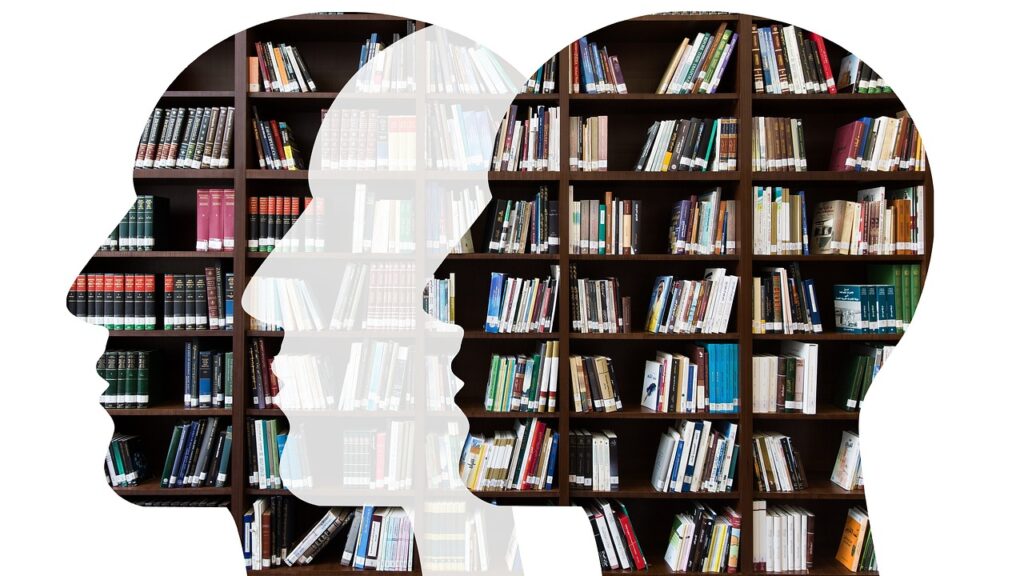
- 質問しながら読む
- こまめに要約する
- 文章のパターンを知る
私が本書から学んだ「読解力をきたえるコツ」を、上記3つの順番で解説していきます。
1. 質問しながら読む
「質問しながら読む」とは、文章に対して「それ本当?」と疑問を持つこと。
質問を考える理由は、本で読んだ内容を「情報」でなく「知識」にするためです。
本書の質問がわかりやすかったので、引用させていただきますね。
みなさんは、「西岡君はカッコいい」と聞いて、どう思いますか?
出典:『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書』
この問いを見て「へえ、そうなんだ」と情報を鵜呑みする人は、読解力の低い人だそうです。
たとえば、
「西岡君ってカッコいいんだって」
とだけ他人に伝えても、「誰の話?」と聞き返されてしまいますよね。
これはただ「情報」を伝えているだけ。
「西岡君ってどの西岡君?」
「誰から見てカッコいいの?」
など疑問を持てば、その後の文章で「西岡君」の情報が出てきた時に「質問の答えだ」と認識でき、「知識」としてインプットできるのです。
このように、情報を鵜呑みにせず質問する意識をもつことで、「わかった気」から、人に説明できるレベルの「知識」に変えることができるということです。
注目するポイントは、次のものがあります。
・著者がはじめに投げかけた問い
・回答が複数考えられるもの
・議論がわかれそうな主張
これらに注目して回答をさがす意識をもつと、著者の伝えたいことがつかめるそうです。ぜひ試してみてください!
2. こまめに要約する
読んだ本の内容を人に説明するのって、難しいですよね。
説明できない原因は「わかった気」になってしまっているから。
本はページ数が多いので、理解していなくても「わかった気」になってしまうのです。
自分のことばで端的に説明できることができて、はじめて「理解した」といえます。では、理解するにはどうしたらよいのでしょうか?
解決してくれるのが、本書の「要約読み」です。
「要約読み」は簡単にいうと、本の内容を一言でまとめて理解を深める方法です。物事を端的に伝える訓練にもなりますよ。
手順は2つです。
- 1節1章ごとに要約的な文章をさがし30字でまとめる
- 1冊読み終えたら本全体の内容を140字でまとめる
私がこの方法を実践して得られた効果を、参考までにお伝えしておきますね!
・読んだ後の「どんな内容だったっけ?」がなくなった
・話の流れが整理できるようになった
・要約メモを見返すと著者の主張がわかるようになった
このように、こまめに要約しながら読むと、頭の中が整理できて内容の理解が深まります。「こんな本でした」と、ひとことで説明できるようになりますよ!
3. 文章のパターンを知る
本を読んでいて「全部が重要な内容に見える」ことはありませんか?
理由は、いま読んでいる部分が全体のどの立ち位置なのか、を把握していないから。
ですが、文章のパターンを知ればこのような悩みを解決できます。
本書の「推測読み」が参考になりましたので紹介します。
「骨」と「身」を見極める
前提として、著者が本当に言いたいことは「1つ」です。
他の重要そうな内容は「論点」であり、「主張」を補強する為のものなのです。
これを本書では、次のように表現しています。
- 本→「魚」
- 著者が伝えたいこと→「骨」
- 論点→「身」
ということは、その本の「骨」である文章を把握できれば、他に重要そうな内容が出てきても「これは身なんだな」と、情報に優先順位をつけられるようになりますよね。
このように、文章の「主張」と「論点」を見極めることで、著者が本当に言いたいことがわかり、内容の理解度もアップします。
文章のパターン4種類
「著者の主張は1つである」とわかったうえで、文章の「パターン」を知っておくと、さらに読みやすくなります。
文章の4つのパターン
①例示:1章で「〇〇は〜だった」と述べて、2章、3章は具体例
②比較:1つの事例を提示したあと、比較対象になる事例を紹介する
③追加:今まで紹介していなかった新しい考え方を提示して、その後に導く
④抽象化・一般化:「こんな経験はありませんか?」→「実はこれができていないから起こってしまうんです」
この4つのパターンを頭に入れておけば、「この文章は追加型だから後でまとめがくるな」というように、客観的に文章を見ることができますよね。
4つのパターンを知ったうえで、本書の「推測読み」をすることで、より理解が深まり著者の主張を外さなくなるといいます。
手順は次の3つです。
・次章を読む前に要約メモを見て復習
・目次で次章のタイトルを見てパターンを推測する
・次章を読みながら、推測の答え合わせをする
私は本を読む前に4つのパターンを書いたメモを読み返すようにしています!
以上が「文章のパターンを知る」という内容でした。
簡単にまとめると、
- 1つの主張+それを補強する論点を見極める
- 文章の4つのパターンを覚える
この2点ができると、著者の主張をより深く理解でき、「読み込む力」が身につきます!
『東大読書』を読んだ感想
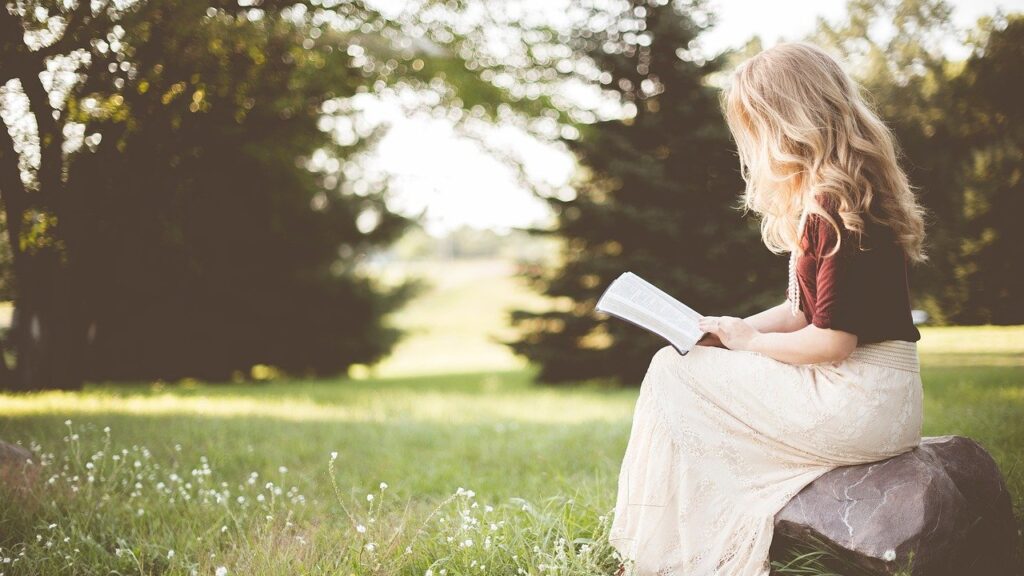
実践できることから試してみよう
本書の読書法は1冊を読むための工程が多いです。
読書初心者がすべてを実践しようと思うと、読書が面倒になりそう…。
なので私は、実践できることから試してみています。
たとえばステップ1で「装丁読み」という方法があるのですが、この工程で付箋をめちゃめちゃ大量に使うのです。
他の読書術の本でも紹介されている方法ですが、本書の場合は装丁から得たヒントを10個以上付箋に書き出します。
さすがに実践できないので、2〜3個思いついたものをメモに残すことから始めています。
このように、考え方はしっかり押さえ、自分が実践しやすい方法で取り入れることが、継続できるポイントかと思います。
本書を読みながら要約練習できる!
「②こまめに要約する」で紹介した、1節1章ごとに30字でまとめる方法。
本書を読んでいる間に練習ができます!
なぜかというと、各節ごとに著者の西岡氏の「一言まとめ」が載っているからです。
1節読んだら自分で要約してみて、西岡氏のまとめを見て答え合わせができるのです。
要約が一致していれば、コツがつかめた!
あまりにも内容がズレていたら、まだまだ練習が必要だ!
なんて思いながら、読み進められますよ。
この練習方法はおすすめです。
初心者は効率より本質
読書術には色々な読み方がありますが、中でも本書は「きたえること」に重点をおいています。
目次を見て読みたい部分だけ拾い読み、速読のため文章を斜め読み、まとめ読み。
これらは一切出てきません。
そもそも読解力、思考力がない状態で効率を求めて読書をしても、自分の知識とならないからだと思います。
私はまだまだ読書初心者なので、本書で紹介されている読み方をマスターして、徐々に効率を重視していこうかと思っています。
まとめ:『東大読書』は、これから読書を始めたい人におすすめ!
ここまで『東大読書』から学んだ「読解力」を身につける方法について解説してきました。
ポイントをまとめます!
- 著者に質問しながら読む
→「情報」から「知識」に変わる - 要約しながら読む
→人に説明できるレベルに理解が深まる - 著者が伝えたい「1つ」のことを見極める
→本題を理解できる、情報を取捨選択できる - 文章のパターンを覚える
→本の全体像が見える
読書法の工程が多いことが難点ではありますが、「本を読むとはなにか」「自分で考えるとはなにか」を丁寧に教えてくれる本でした。
すべて実践できなくても、徐々に取り入れていけば読解力はアップします。私はまだ道半ばですが、効果を実感できている点もあります。
読書に苦手意識がある方が読むと、私のように「こんな読み方があったんだ!」と感動できるかと思います。
ぜひ全文を読んで、「東大読書」を体感してみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
「読んでみたいけど難しそう…」という方は、漫画版もあります!
本をたくさん読むならKindle Unlimitedがおすすめです。
月額980円(税抜)で200万冊以上の本が読み放題!
月に3冊以上読めばもとが取れます。
最初の30日間の無料体験 & いつでもキャンセル可能
ぜひ試してみてください。