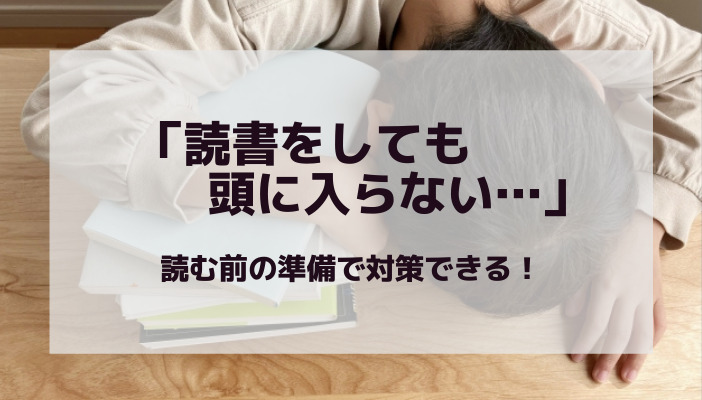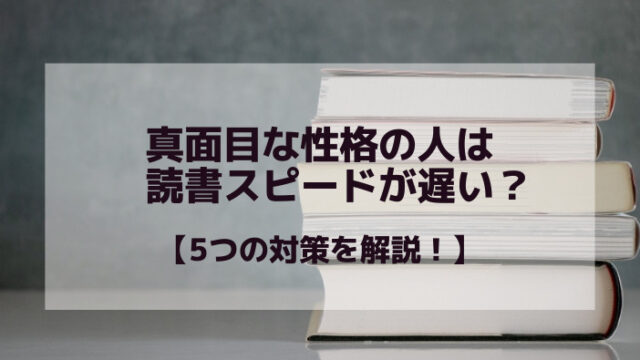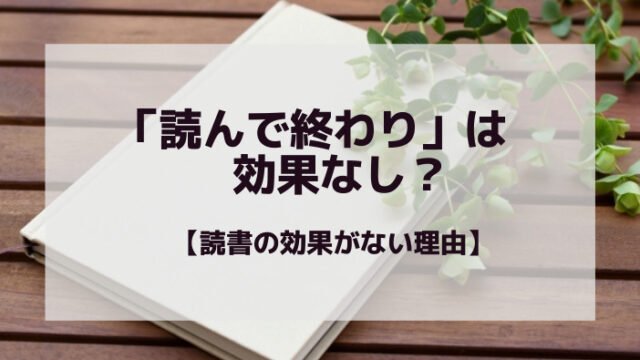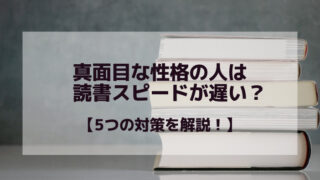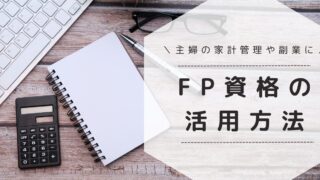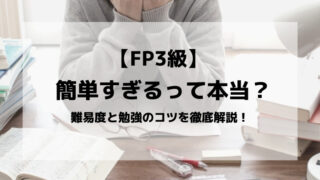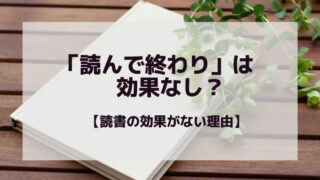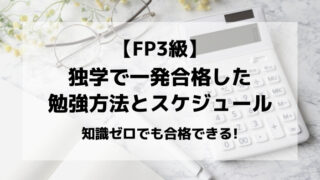- 真剣に読書をしているのに内容が頭に入らない…
- 気づいたら活字を目で追ってるだけになっている…
このような悩みを解決する記事です。
この記事を読めば、「読書をしても頭に入らない」悩みを解消し、がんばって読書をした時間が無駄にならなくなりますよ。
結論、読書をしても頭に入らない原因は「読書前の準備不足」です。
なので、「読書前の準備」をすることで解決できます。
以前は私も読書の内容が頭に入らないことがありましたが、読書前の準備を取り入れたら解決しました。
本記事では、「読書をしても頭に入らない原因」「5つの解決方法」「読書前の準備を取り入れて筆者が実感した変化」について解説します。
- 読書術の本15冊を読了
- 実践して再現性の高かった方法のみを紹介
本記事の参考にした本は、以下の記事で紹介しています。
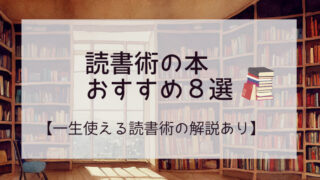
読書をしても頭に入らない原因は準備不足
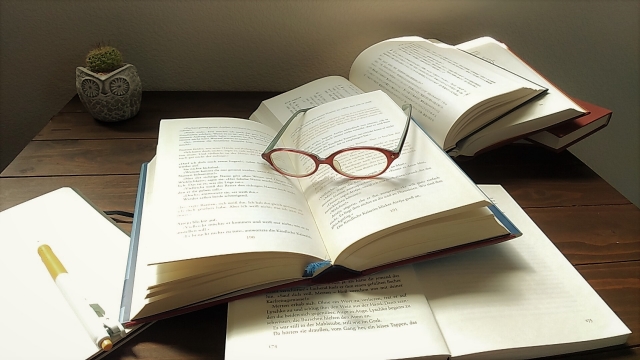
冒頭からお伝えしている「読書前の準備」とは、ザックリ分けると以下の2点を行うことです。
- 目的を決める
- 予備知識をつける
この2点が大事な理由について、順番に解説します。
- 目的がないと目につく文章がない
- 目的がないとモチベーションが続かない
- 予備知識がないと理解できない
- 予備知識がないと目につく文章がない
目的がないと目につく文章がない
まずは「目的を決めること」が大事な理由から解説します。
目的がなく読書をすると、目につく文章がないため内容が頭に入りません。
なぜなら、人の脳は意味のある文章に惹かれるからです。
このような経験はありませんか?
テレビ番組の占いで「今日のラッキーカラーは”赤”だ」と見たら、一日中赤いものばかり目につく
上記は”カラーバス効果”といい、ある物事を意識するとそれに関連するものが目にとまる、という現象のことです。
つまり読書をするうえで「これを知りたい!」という目的がなければ、目にとまる文章がなく内容が頭に入ってきません。
目的がないとモチベーションが続かない
目的がなければ、読書のモチベーションも続きません。
モチベーションが下がった状態で読書をすると、
- 気づいたら他のことを考えている
- ぜんぜん集中できない
- 眠くなってくる……
など、本を開いているけど内容は入ってこない状態になりやすいですよね。
モチベーションが上がりワクワクしている状態だと、記憶を促進してくれるドーパミンという物質が分泌される効果があります。
なので、ワクワク感のない状態での読書は、集中できず記憶にも残らない無駄な読書の時間となってしまいます。
予備知識がないと理解できていない
次に「予備知識をつける」が大事な理由について解説します。
人は、「何の話か」がわからないと理解できないため、内容が頭に入りません。
たとえば、次の場面を想像してみてください。
友人2人が会話しているところに、あなたが途中から参加した
何の話題で盛り上がっているのかわからず、「何の話してるの?」と質問しますよね。
話題が「友人Cさんについて」だと事前に知っていたら、
「いつも成績がいいよね」「愛嬌があるよね」という会話を聞いただけで、すぐにCさんの顔が思い浮かびますよね。
読書も同じで、「何の話か」のヒントがなければ文章を理解できないのです。
ヒントを得る方法は、後半の「5つの解決方法」で解説します。
予備知識がないと目につく文章がない
予備知識を得ると、目的の部分で解説したカラーバス効果も有効です。
たとえば、本の帯を見て、「この本のキーワードは”読書=投資”だ」とわかったとします。
すると、文章を読んだときに「利率」や「リターン」など、投資に関連する単語が目につきますよね。
目につく単語や文章があれば、なんとなく流し読みで終わってしまうことがなくなります。
「読書をしても頭に入らない」を解決する5つの準備

ここまで、読書をしても頭に入らない原因は「読書前の準備不足」だとお伝えしてきました。
「読書前の準備」とは、ザックリ分けると以下の2点を行います。
- 目的を決める
- 予備知識をつける
この2点について、私が実践している方法を5ステップで解説します。
- 目的を決める
- 読書後の行動を決める
- レビューで本の概要をチェック
- 装丁・著者情報で予備知識をつける
- 目次で予備知識をつける
ステップ1:目的を決める
まず「本から何を学びたいか」など目的を決めます。
目的を決めてから読書をするメリットは次のものがあります。
- 目的に沿った本選びができる
- 読むときのモチベーションが上がる
- 目的に沿った文章が目にとまる
・目的に沿った本選びができる
「いま解決したい悩み」や「習得したいこと」を書き出してみると、自分がいちばん興味のあることがわかります。
・読むときのモチベーションが上がる
「人気の本だから読む」という理由よりも、「自分が解決したい悩み」に沿った本を読んだ方がモチベーション高く読むことができます。
・目的に沿った文章が目にとまる
先にも述べましたが、目的を意識して読むと関連した文章や単語が目にとまるようになります。
目的はいまの悩みに沿った内容にすると良いでしょう。
例として、私が読書術の本を読み始めたときは以下の目的を設定しました。
- 短期間でたくさんの本を読む法を知りたい
- 本から得た知識を活用する方法を知りたい
そして選んだうちの1冊が『レバレッジ・リーディング』という、多読の方法を解説した本でした。
決めた目的は、紙やスマホのメモ機能などに書いておくと忘れないですよ。
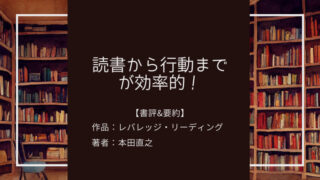
ステップ2:読書後の行動を決める
ステップ1で作成した目的を書いた紙に、読書後の行動も書いておきます。
読書後の行動を決めるメリットは次のものがあります。
- 行動をする前提だと文章が目にとまりやすい
- 読書のモチベーションを継続できる
例として、私が決めた行動目標は以下の内容でした。
- 1カ月で10冊読めるようになる
このような行動目標があると、「1ヶ月で10冊読むために役立つ情報は?」の回答をさがす感覚で読めるのです。
つまり意味のある文章が目にとまりやすくなるということです。
また、行動目標があるとモチベーションを継続でき、読んだ内容が記憶に残りやすくなります。
前回読んだ内容を覚えていれば、続きから読んだときに内容が頭に入りやすくなりますね。
ステップ3:本の概要をレビューでチェック
本を購入する前に、レビューを見て概要をチェックします。
概要をチェックするメリットは次のものがあります。
- 目的に沿った本を選べる
- 評価の低い本を避けられる
- 自分のレベルに合った本を選べる
・目的に沿った本を選べる
たとえば、”読書術”というカテゴリーのなかでも、速読重視、記憶定着重視、読解力重視など本によって内容がちがいます。
ステップ1で決めた目的に沿った内容なのか、事前にチェックすると本選びに失敗しません。
・評価の低い本を避けられる
他人の評価を鵜呑みにする必要はありませんが、あまりにも評価が低い本は内容が薄い可能性もありますので、事前に知っておくとよいでしょう。
・自分のレベルに合った本を選べる
いまの自分のレベルに合った本でなければ、興味が薄れて内容が頭に入らない原因となります。レビューで難易度について記載があれば、チェックしておくとよいでしょう。
その分野の知識がなければ初心者向け、ある程度詳しい分野なら中級者・上級者向けの本を選ぶのがおすすめです。
概要を把握するためのツールは、次のようなものがあります。
- Amazonのレビュー
- ブログなど書評サイト
- 本要約サービスflier
Amazonレビューや書評サイトは、その本を読んだ読者の感想をザッと見ます。
本要約サービスflier(フライヤー)は、プロのライターによって要点がまとめられているため、本の要点を把握するのに便利です。
ステップ4:装丁・著者情報で予備知識をつける
本を購入したら、まず本の要旨・著者の人物像を把握します。
これがけっこう大事です。
- 本文の理解が早くなる
- 著者の主張を読み取りやすくなる
「何の話をどんな人が話すのか」を把握しておくと、本文を読んだときの理解が早くなり内容が頭に入りやすくなります。
具体的には次のものをチェックします。
- 装丁(表紙や帯)
- 著者情報、はじめに、おわりに
・装丁(表紙や帯)
表紙や帯に書かれたキーワードを見て、本の要旨を把握できます。
・著者情報、はじめに、おわりに
著者が読者に伝えたいことや、どんな背景があってその本を書いたのかなどを把握できます。
これらを把握しておくことで、本文を読んだときに内容の理解が深まり、頭に入るようになります。
ステップ5:目次で予備知識をつける
最後に目次をチェックします。
目次をチェックするメリットは次のものがあります。
- 本の文章構造を把握できる
- 知りたい情報が書かれている箇所がわかる
・本の文章構造を把握できる
どのような流れで話が進むのかを把握していると、文章を読んだときの理解が深まります。
1章は著者の主張、2章は具体例、3章はおすすめの書籍、のようにザックリとでも把握しておくと、客観的に本を読めるようになりますよ。
・知りたい情報が書かれている箇所がわかる
知りたい情報が書いてあるページまで、どのくらい読めばいいのかわからず読み始めると、途中でモチベーションが続かなくなります。
目次の見出しから、知りたい情報が書いてありそうな箇所を把握しておくことで、読みたい部分までの量感がつかめるためモチベーションを継続できます。
以上が、「読書をしても頭に入らない」を解決する5つの準備でした。
読書の内容が頭に入るようになって変わったこと

ここからは、「読書前の5つの準備」を取り入れる前と後で、どのような変化があるのか。
読書の内容が頭に入らなかった筆者の体験談を解説してきます。
私が実感している変化は以下の3つです。
- 読書中にボーッとしなくなった
- 知りたい情報を得られるようになった
- 読書が楽しくなった
読書中にボーッとしなくなった
読書中にボーッと他のことを考える瞬間がなくなり、本の内容に集中できるようになりました。
「これを学びたい!」ということを決めて文字で書き残しているため、モチベーションが維持できているのだと思います。
以前も、何かしら学びたいと思って読書していましたが、見える化したほうが効果があると実感しました。
ボーッとしない分、読んだ内容を覚えていますし、速く読めるようにもなりました。
知りたい情報が得られるようになった
「知りたいことはこれ」「その答えはこれ」と、整理して残せるようになりました。
以前から、重要そうな文章にはマーカーを引いて…みたいなことは実践していましたが、目的が決まっていないためマーカーだらけになって、結局なにも覚えていない状態でした。
現在は、目的に沿った本を選び、本の中でも特に知りたい箇所に目星をつけて読むため、情報の整理ができているのだと思います。
読書が楽しくなった
ワクワクして本を読めるし、読書をした実感が湧いて楽しくなりました。
以前は「読書をしなくては…」という義務感で本を読んでいたため、楽しいと思うことはありませんでした。
現在は、表紙や著者情報を見て自分なりの仮説を立て、本文を読むなどしているため、答え合わせをする感覚で楽しく読書ができています。
また、「知りたい!」という欲求が満たされているため、満足感があるのだと思います。
「早く次の本も読みたい」という感覚は、人生で初めてですね。
まとめ:読書前の準備をすると内容が頭に入るようになる
ここまで、「読書をしても頭に入らない原因」「解決方法5ステップ」「読書の準備をして変わったこと」について解説してきました。
長々と解説しましたが、大事なことは2点です。
- 目的を決めること
- 予備知識をつけること
「読書をしても頭に入らない」悩みを解消して、楽しい読書ライフを過ごしましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。