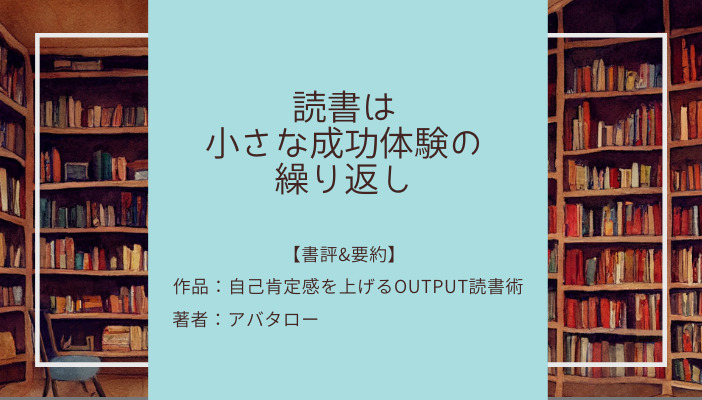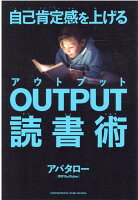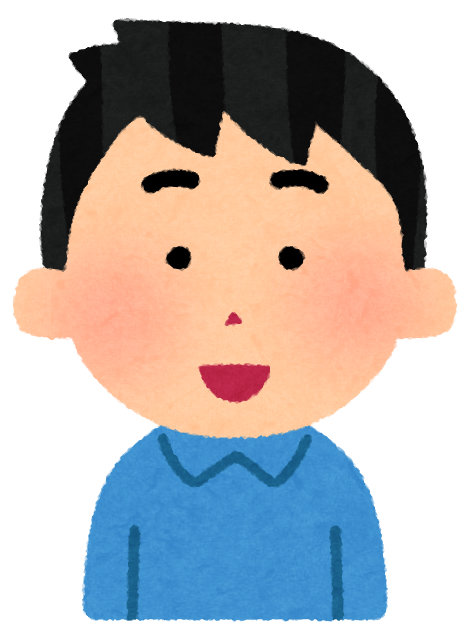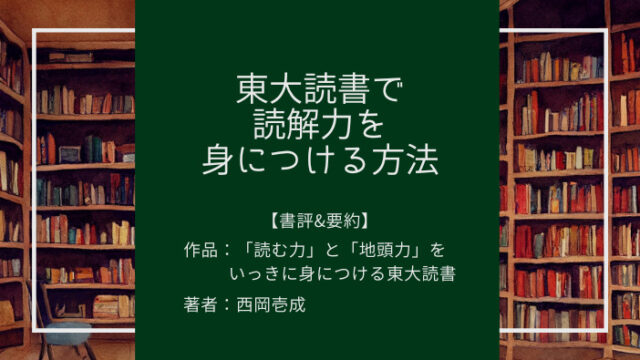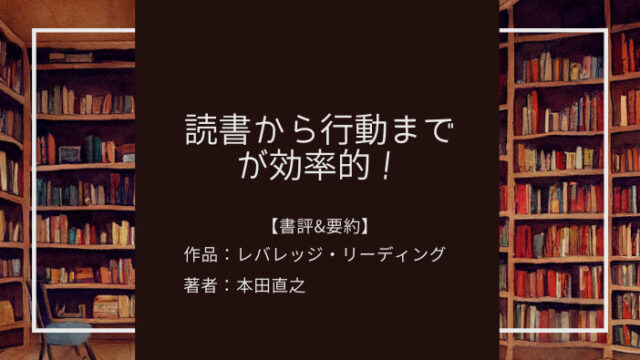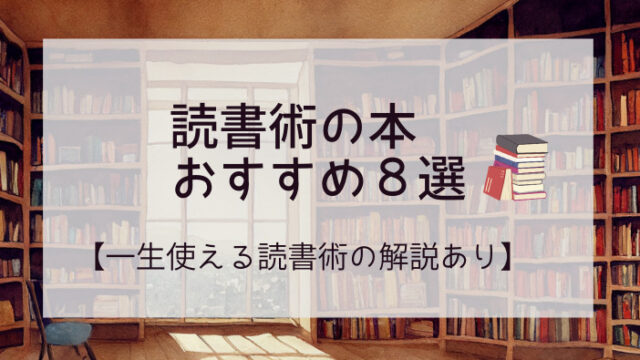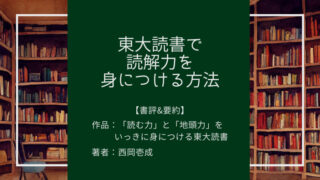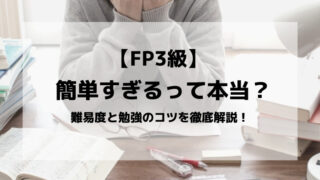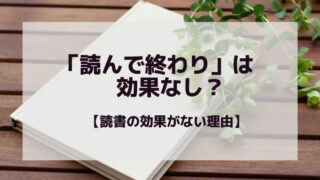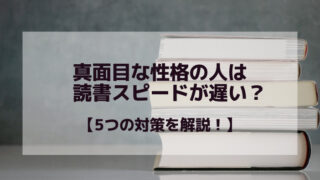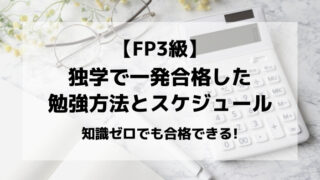こんにちは、いちはです。
今回ご紹介するのは、私が読書ブログを書くキッカケとなった1冊、
『自己肯定感を上げるOUTPUT読書術』です。
読書の読解力が低いと落ち込んでいたときに「自己肯定感」という文字が目に止まり、読んでみました。
著者は書評YouTuberのアバタロー氏。
本書は、自信が持てない読者へ向けて、
「読書によって人生を好転させることができるよ!」という、著者からのあたたかいメッセージが詰まった本です。
本記事では、以下のポイントにしぼって本書を解説していきます。
- 自己肯定感を上げるOUTPUT読書術とは?
- 読書が自己肯定感を高めるとは?
- OUTPUT読書術の手順とは?
- 失敗しない選書の方法とは?
読書術のおすすめ本を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
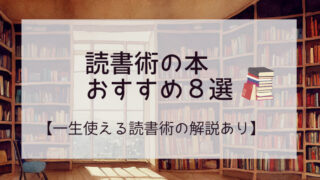
「自己肯定感を上げるOUTPUT読書術」はどんな本?
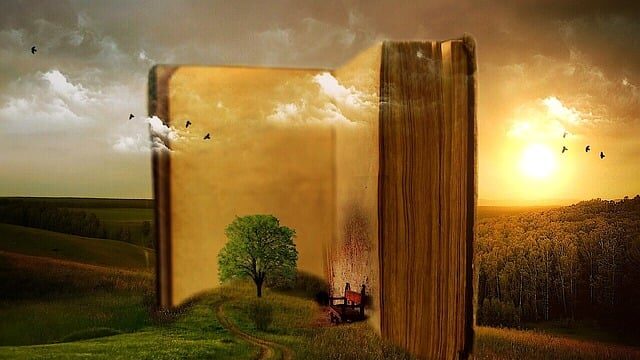
冒頭でもお伝えしましたが、本書のテーマは「読書によって人生を好転させることができる」ということ。
著者は、読書について次のように述べています。
読書とは小さな成功体験の繰り返し
引用:自己肯定感を上げる OUTPUT読書術 (p.74)
OUTPUT読書術とは、成功体験の繰り返しによって、自己肯定感を上げる読書法なのです。
読書によって成功体験をどのように積み重ねていくのか。
本書の構成は以下のとおりです。
1章 人生を劇的に変える読書の威力
2章 超効率的なOUTPUTフローが、無限の可能性を引き出す
3章 OUTPUT読書術の具体的な方法
4章 絶対失敗しない選書の方法
こんな人にオススメ
本書を読むのがオススメなのは、次のような方です。
- 自信を持つきっかけが欲しい
- 読書をこれから始めたい
- 読書を習慣化できない
- 読書内容をアウトプットするコツが知りたい
私が読んだ理由
- 自己肯定感を上げる方法に興味があったから
- 読書術の本ランキングで上位にあったから
著者情報
本書の内容解説の前に、著者アバタロー氏がどのような人物なのか、ご紹介します。
- 書評YouTuber
- 早稲田大学文学部卒業
- 日中は某外資系企業にて管理職をつとめるサラリーマン
- 趣味である読書の延長として書評YouTubeを開設したところ、2020年1月に大ブレイク。
- 「読書が苦手な人でも古今東西の難解な名著がラジオ感覚で楽しめるチャンネル」として話題となり、現在も配信活動を続けている。
上記のように、書評YouTuberとして活躍されているアバタロー氏ですが、じつは高校生までは読書が嫌いで、自分に自信がもてなかったとのこと。
読書を好きになったキッカケは、ある恩師のことば。
それから大学は文学部を目指し、読書を重ね、読書によって人生が好転したそうです。
そんなアバタロー氏が変わるキッカケとなった読書術が、本書で紹介されています。
まずは読書と自己肯定感の関係について、解説していきます。
読書で自己肯定感が上がるとは?

そもそも「自己肯定感」って具体的に何? と疑問に思いまして、調べました。
心理学っぽい内容ですが、前提として知っておいた方がわかりやすいので、少々お付き合いください。
自己肯定感は6つの感覚で構成されている
自己肯定感の定義はこちらです。
・自己肯定感とは
自分のあり方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する語。
出典:実用日本語表現辞典
要するに、「ありのままの自分でいいんだ!」と思える感覚ですね。
さらに、自己肯定感は6つの感覚で構成されています。
- 自己有用感:自分は何かの役に立っているという感覚
- 自己決定感:自分で決定できるという感覚
- 自己信頼感:自分を信じられる感覚
- 自己効力感:自分にはできると思える感覚
- 自己受容感:ありのままの自分を認める感覚
- 自尊感情 :自分には価値があると思える感覚
これら6つの感覚を高めることで自己肯定感も上がる、ということなんですね。
本書の読書術では、次の2つの要素をカバーできるのです!
- 自己効力感
- 自己決定感
順番に解説していきます。
読書ログが達成感を生み出す
自己肯定感を上げる要素の1つめは、読書を習慣化して「読書ログ」をつけること。
これにより、「自己効力感」を高めることができます。
「自己効力感」という概念を提唱した、カナダの心理学者アルバート・バンデューラによると、自己効力感を高める重要な要素の1つは「直接的達成体験」だといいます。
本書で紹介されている「読書ログ」の書き方はこちらです。
- タイトル
- 読書開始日
- 読了日
- 感想
読書を習慣化し、この読書ログが増えていくと、自分の成長が一目でわかりますよね。
たとえば、過去と比べて「読むスピードが速くなった」「感想のまとめ方が上達した」など、それぞれ感じることがあるはずです。
つまり、読書と読書ログの作成を繰り返すことで、「2つの達成体験」ができるのです。
このように、読書ログの習慣化によって「直接的達成体験」を味わうことができ、自己肯定感を構成する「自己効力感」を高められます。
成長を実感できると、自信がついてきますよね!
自分で考え抜いた経験が自信につながる
自己肯定感を上げる2つめの要素は、情報を取捨選択すること。
これにより「自己決定感」を高めることができます。
本書の読書法では、自分にとって重要だと思った内容に付箋を貼っていきます。そして、最終的に残す付箋を3つだけ選びます。
重要な文章へマーカーを引きながら本を読んでいると、
気付いたらマーカーだらけ…
みたいな経験ありませんか?
仮に20個の文章にマーカーを引いたとしても、すべてを記憶しておくのは難しいですよね。なので、「一生記憶に残しておきたい情報は3つまで」と上限を決めるのです。
ポイントは、その本の重要な内容ではなく、自分にとって重要だと思う内容を選ぶこと。
なぜなら、この行動が「自己決定」だからです。
自己決定感は、自分で決定できるんだという感覚を味わうことで、高められていきます。読書だと、以下の役割となります。
- その本のなかで重要な内容→他者(著者)の意見
- 自分にとって重要な内容→自分の意見
つまり、自分の意見の中から、大事なポイントを取捨選択して選び抜いた行動が「自己決定感」を生み出すということなのです。
そして「自己決定感」が高まると、自己肯定感も上がる! ということです。
「自己肯定感を上げるOUTPUT読書術」の手順
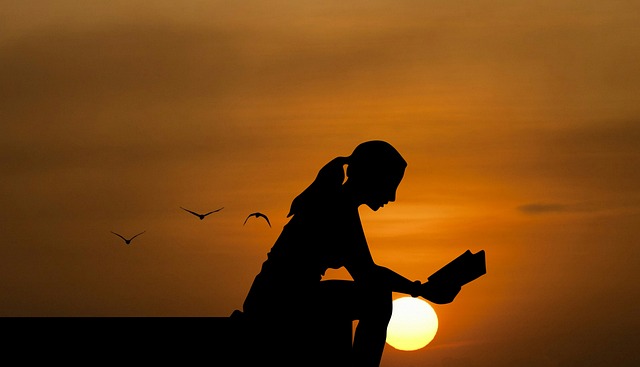
読書が自己肯定感を上げる理由がわかったところで、次は具体的な手順を解説します。
これまで読書術の本を10冊以上読んできましたが、本書の手順はシンプルでわかりやすい! 入門書としておすすめしたい1冊ですね。
本書の読書術の基本骨格は4つです。
- 準備
- 読解
- 要約
- 発信
この基本骨格を進めていく上での要点を、6項目ご紹介します。
ネタバレしない程度にサクッと書いていきます!
1. 視界をデザインする
読書を始める前に、集中できる環境を整えましょう。
主に「視覚環境」を整えると、集中力がアップするそうです。
ポイントは、読書で必要な道具以外は片付けること!
2. 仮説を導き出す
視界が整ったら、次は仮説を立てます。
表紙、帯、目次を見て「こんな内容だろう」と仮説を立てると、本文を読んだ時の読解力が上がります。
コツは、「5W1H」を意識すること!
3. 言葉の「温度」を拾い読む
1ページ目からじっくり読まず、拾い読みから始めます。
「著者の感情」に着目すると、著者の主張を読み取りやすくなります。
主張が強い部分には、線を引きながら行います!
4. ツッコミモードに切り替える
「問い」「主張」「根拠」に、頷いたり疑問をもちながら再読します。
著者にとって重要な部分はペン
自分にとって重要な部分は付箋
と役割を分けて目印をつけていきます。
5. A4用紙1枚にまとめる
線を引いた部分、付箋を貼った部分をたどって、分かりやすい言葉でまとめていきます。
本書でテンプレートが紹介されていますので、それを見ながらできます!
6. 思考を深める
⑤でまとめた内容を発信します。
ポイントは、相手に伝わるレベルに噛み砕いて説明すること。
発信方法は、自分が得意なものでOKです。(話す、描く、書く)
本書では次の方法が紹介されています。
- 話す:YouTube
- 書く:ブログ、Twitter、書評サイト
- 描く:図解、4コマ漫画をSNSで投稿
発信すると、自分がちゃんと理解できているかの確認ができるため、思考が深まります。
以上がOUTPUT読書術の読書手順です。
個人的には「③ツッコミコード」でペンと付箋の役割を分ける、という点が特に参考になりました。
「その本がどんな内容なのか」と「その本を読んで自分がどう思ったのか」を分けて管理しておくと、頭の中が整理できるのでオススメです!
失敗しない選書のコツ
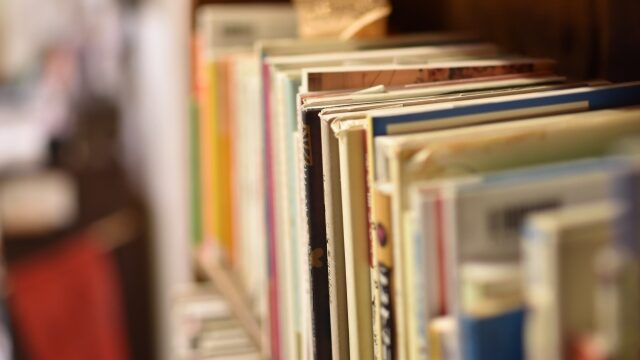
読書のコツがわかると、本をたくさん読みたくなりますよね!
ですが、時間もお金も無限にあるわけではありません。
読書の時間とお金を無駄にしないためには、本を選ぶコツも知っておきたいところです。
本書で紹介されている選書のステップは、次の3つです。
ステップ1 読むべき本の方向性を決める
ステップ2 読むべき本のテーマを決める
ステップ3 読むべき本の予算を決める
特に興味深かったのは「選書は分散投資」という考え方。
投資の原則として、リスクを軽減するために購入時期や銘柄などを分散する、という理論がありますが、本を選ぶ際も同じだと著者はいいます。
上記のステップで決めたテーマ、予算の範囲で10冊の本を購入するとします。
その際、次の5つのカテゴリーに該当する本を選びます。
- 第一人者の代表作
- 分かりやすい本
- ベストセラー本
- 古典的名作
- 最新作
たしかに、この条件に合った本を読んでおけば、その分野の知識を網羅的に得られますよね!
著者は特に「古典」をオススメしており、その理由を次のように述べています。
「古今東西変わらない普遍的な知恵を学べる」
引用:自己肯定感を上げる OUTPUT読書術 (p.169)
「偉大な賢者から力を借りることができる」
古典は難しいので、私はその分野の「わかりやすい本」から始めて何冊か読み、基礎知識が備わったら古典に挑戦するようにしています!
まとめ
ここまで、『自己肯定感を上げるOUTPUT読書術』の要点について解説してきました。
簡単にまとめます!
- 自己肯定感とは「ありのままの自分でいいんだ」と思える感覚。
- 読書によって、自己肯定感を構成する要素を高めることができる。
①読書を習慣化して達成感を味わうこと
②他人に左右されず、自分の意見を決めること - 選書のコツは、分散投資である。
OUTPUT読書術は「小さな成功体験の繰り返し」。つまり、継続することで効果が発揮されます。
継続するコツについて、著者は次のように述べています。
「自分のペースを崩さないこと」──これがOUTPUT読書術の大原則です。
自己肯定感を上げる OUTPUT読書術 (p.62)
他人と比較して「読むのが遅い」「理解力が低い」と落ち込むのではなく、「過去の自分からどれだけ成長できたか」を感じることが重要なのですね。
冒頭でもお伝えしましたが、本書がキッカケで、私は読書についてのブログを書こうと思いました。
アウトプットすることはまだ不慣れですが、1冊読み切って1記事完成できたときの達成感は、少しずつ私に自信を与えてくれています。
無理のない範囲で読書を習慣化し、自己肯定感を上げていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本をたくさん読むならKindle Unlimitedがおすすめです。
月額980円(税抜)で200万冊以上の本が読み放題!
3冊以上読めばもとが取れます。
最初の30日間の無料体験 & いつでもキャンセル可能
ぜひ試してみてください!