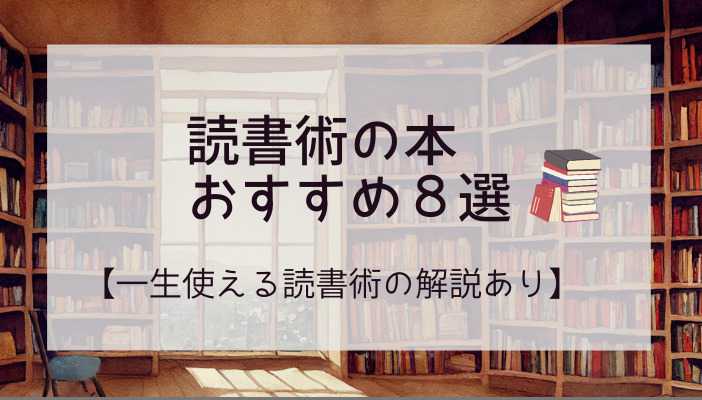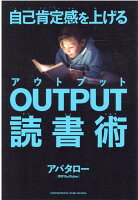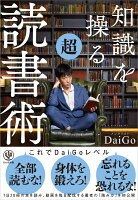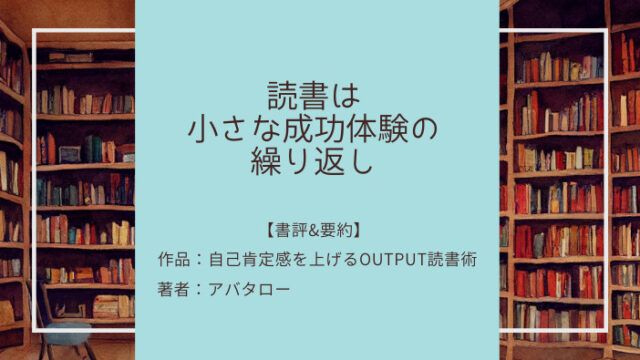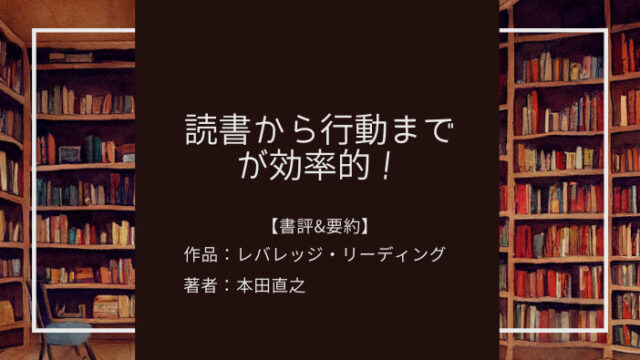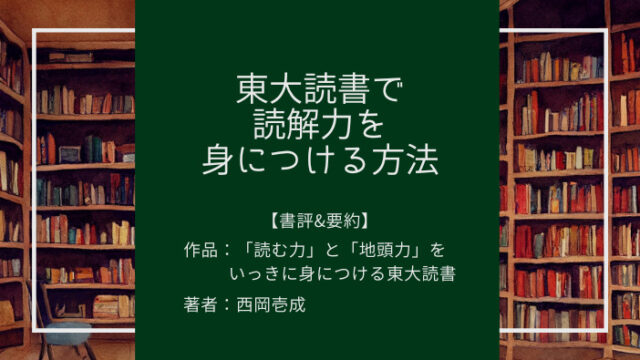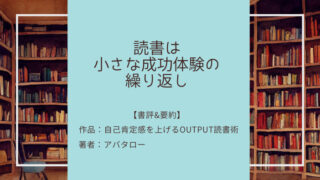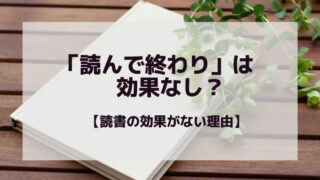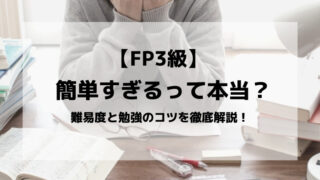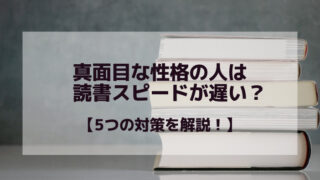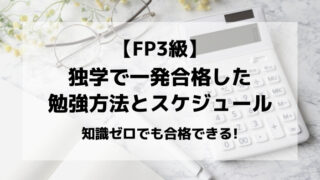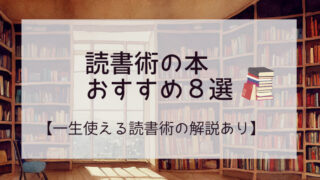- 読書術の本がいっぱいあるけど、どれを読めばいいの?
- 読書術って色々あるけど、結局どれを試したらいいの?
このような悩みを解決します。
この記事を読めば、あなたの目的に合った読書術の本を選ぶことができます。
私も読書のコツをつかみたくて読書術の本を調べましたが、とにかく種類が多い……。
ということで、15冊を読み漁りました!
複数冊読むうちに、どの本にも共通している点や、著者によって意見が異なる点がわかってきました。
そこで本記事では、15冊の中で役に立った8冊を厳選して紹介します。
また、後半では一生使える読書術を5つ解説します。8冊に共通する読書術のため、信憑性があります。
- 読書術の本15冊を読破
- 実際に読んで役に立った8冊を厳選
ぜひ参考にしてみてください!
読書術の本おすすめ8選

今回ご紹介するのは以下の8冊です。
本のタイトル名をクリックすると、該当の本の解説まで一気にスキップできます。
気になる本がありましたら、そこだけ読んでいただいても大丈夫です!
ちなみに、「読みやすさ」評価については、読書に慣れていなかった私が読んで感じた難易度です。
難しい本は苦手だ、という方は参考にしてください。
それでは解説していきます!
自己肯定感を上げるOUTPUT読書術
| 読みやすさ |  |
| ページ数 | 214ページ |
1冊目は『自己肯定感を上げるOUTPUT読書術』です。
著者は書評YouTuberのアバタローさん。
読書術の手順がシンプルなので、8冊の中でいちばん実践しやすいかと思います。
図解が多く読みやすいこともあり、初心者の方におすすめの1冊。
本書の目的は、読書をキッカケに自己肯定感を上げ、人生を好転させること。
「自分のペースでいい」「全部読まなくていい」など、著者の優しいことば選びも本書の特徴の1つ。
読書の内容をブログやSNSで発信したい! という方にも参考になる本です。
- これから読書を始めたい
- 読みやすい本がいい
- 実践しやすい読書術がいい
- 自分に自信を持ちたい
読んだら忘れない読書術
| 読みやすさ | 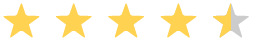 |
| ページ数 | 251ページ |
2冊目は『読んだら忘れない読書術』です。
『アウトプット大全』が大ヒットした、樺沢紫苑さんの読書術の本。
タイトルにある通り「忘れないこと」を重視した読書術を学べます。
読書の目的は行動を変えること。
そのためには「内容を覚えていないと意味がない」と主張し、速読よりも深読、多読よりも1冊を丁寧に読むことを勧めています。
本書のポイントはアウトプットとスキマ時間。
脳のしくみを利用した読書術により、内容を忘れないうえ習慣化もできてしまう一石二鳥の読書術です。
また、「ワクワク読書術」「ギリギリ読書術」などネーミングがかわいい点が個人的にお気に入りポイントです!
- 本の内容を忘れてしまう
- 読みやすい本がいい
- 実践しやすい読書術がいい
- 読書を習慣化したい
知識を操る超読書術
| 読みやすさ |  |
| ページ数 | 240ページ |
3冊目は『知識を操る超読書術』です。
毎日10〜20冊の本を読むというメンタリストDaiGoさんの読書術の本。
本書は「3つの嘘」と題し、一般的な速読、多読、選書をバッサリと否定することから始まります。
本を読むスピードに関しては「4分の3は遺伝で決まる」というショッキングな事実も判明!
そのうえで、視線を速く動かす「速読」ではなく、記憶に定着させつつ速く読める効率的な読書術を伝授してくれます。
エビデンスが豊富なことで有名なDaiGoさん。
研究事例の細かい内容まで紹介されている点も、本書の魅力の1つです!
- 本の内容を説明できるようになりたい
- 本をたくさん読む方法を知りたい
- 読書の研究事例に興味がある
レバレッジ・リーディング
| 読みやすさ |  |
| ページ数 | 171ページ |
4冊目は『レバレッジ・リーディング』。
出版が2006年とやや古いのにも関わらず、いまでも読書術の本ランキングで上位に入っている人気の書籍です。
本書は効率的に多読し、行動に移す方法がわかる本。
「100倍の利益を稼ぎ出す」という副題の通り、
少ない労力で多くの利益を生み出す「投資としての読書術」を学べます。
効率重視なので、読書ノートの方法がシンプルで無駄がない!
それでいて、条件反射的に行動に移せるという超効率的なメゾットとなっています。
また、読書を習慣化するコツや選書の方法について、著者が実践している方法がわかる点も本書の魅力。
読書をする時間がないビジネスパーソンにおすすめの1冊です!
- 読書の知識を仕事に活かしたい
- 読書を習慣化したい
- 本をたくさん読む方法を知りたい
死ぬほど読めて忘れない高速読書
| 読みやすさ |  |
| ページ数 | 240ページ |
5冊目は『死ぬほど読めて忘れない高速読書』です。
本書のテーマは「スピード」と「記憶定着」。
高速読書は「1冊を30分で3回」読む読書術です。
「30分で読んでも記憶に残らないのでは?」と思いますよね。
それが記憶に残るんです。
脳科学に裏付けされた根拠のもと、長期記憶できるノウハウが詰まっているのが本書の高速読書なのです。
読書前の準備から行動に移すまで、一通りの流れを学べます。
こちらも『レバレッジ・リーティング』と同様に、読書メモの取り方がシンプルです!
- 1冊の本を読みきれない
- 速く読む方法を知りたい
- 読書の知識を仕事に活かしたい
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書
| 読みやすさ |  |
| ページ数 | 282ページ |
6冊目は『東大読書』です。
著者は偏差値35から東大に合格した経験を持つ西岡壱成さん。
本書で紹介されている「能動的な読書」をキッカケに、東大レベルまで成績がアップしたといいます。
一言で言うと「本を使って思考力を鍛える」読書術です。
本書では効率を求めておらず、地頭が良くなり読解力も上がれば、自然と読書スピードは速くなるという考え。
本とトコトン向き合い議論して、思考を深める方法を学ぶことができます。
個人的には、自分では決して思いつかない読み方や考え方を知ることができ、読書をすることが楽しくなった1冊です!
- 読書を通して思考力を鍛えたい
- 読解力を鍛えたい
- 東大生の読書術を知りたい
偏差値95、京大首席合格者が教える「京大読書術」
| 読みやすさ |  |
| ページ数 | 208ページ |
7冊目は『京大読書術』です。
著者の粂原圭太郎さんいわく、京大生は「狭く、深く」学ぶ特徴があるのとのこと。
本書では、読書で「深く」知識を身につけ発想力を鍛える方法を学べます。
前提として読解力は必須となるため、1章では読解力の身につけ方も紹介。
また、速読について「考えずに読むと効果がない」と前置きしたうえで、速読のコツについても紹介されています。
特に参考になったのは「どんな発想もゼロからは生まれない」という考え方。
「知識と知識のつなげ方」についてわかりやすく解説されているため、幅広く読書をしたくなりました!
- 読書で思考力を鍛えたい
- 読書で知識の幅を広げたい
- 速く読むコツを知りたい
本はどう読むか
| 読みやすさ |  |
| ページ数 | 182ページ |
最後8冊目は『本はどう読むか』です。
著者は昭和を代表する知識人、社会学者の清水幾太郎さん。
著者自身の人生を振り返りつつ、本とどう向き合ってきたか、どんな読書術を実践してきたかを紹介している本です。
著者の読書経験を通して「何のために読書をするのか」を学ぶことのできる1冊。
時代背景が現代とちがう点での読みづらさはありますが、文章構造が整っているため、意外とサクッと読めます!
個人的にいいと思ったポイントは、読書術についての失敗談も書かれているところ。
こんな立派な方でも失敗を繰り返し試行錯誤していたんだ、と励みになりました。
また、試行錯誤のすえ確立された本書の読書術は、最近の読書術にも反映されています。
先人の失敗経験を経て、最適な読書術が現代に浸透しているのだとわかり、面白いですよ!
- 読書論や教養について学びたい
- 読書の目的を改めて考えたい
一生使える5つの読書術を解説
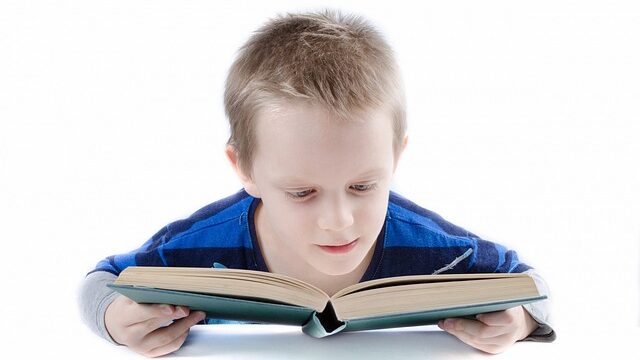
読書術には速読、精読、多読などさまざまあり、目的によって使い分けが必要です。
今回ご紹介した8冊も、著者によって読書術が異なります。
しかし、読書術に関する本を読んでいくうちに、どの本にも共通して紹介されている方法があることがわかりました。
共通して紹介されている方法は、以下の5つです。
- 想定読み
- マクロからミクロ
- 予測読み
- ツッコミ読み
- 要約読み
共通しているということは、読書においてベースとなる考え方だということ。
それぞれ出版された時代や著者の背景は異なりますが、読書をする上で基本となる考え方です。
つまり、どんな目的でもどの時代でも使える読書術!
覚えておけば一生使える方法です。ぜひ参考にしてみてください。
それでは1つずつ解説していきます!
装丁読み
装丁とは表紙や帯、裏表紙などのことです。
「想定読み」は、本を読む前に装丁を見て、本のテーマや重要なキーワードをチェックしておく方法です。
この方法の効果は次のものがあります。
- 事前情報があると内容を理解しやすい
- 著者の主張をつかめる
表紙や帯に書かれているコピー文などは、その本の魅力を端的に伝えるために考えられたワード。
著者が伝えたいことや、本筋となるキーワードが詰まっています。
これらを事前にインプットしておくと、本の内容の理解度が上がり、スムーズに読み進めることができます。
また、著者情報を事前に調べておくこともおすすめです。
マクロからミクロ
1冊の本を、全体をざっと読んでから2回目にじっくり読む方法です。
- 1回目:全体像を把握する(マクロ)
- 2回目:重要な部分をじっくり読む(ミクロ)
この方法の効果は次のものがあります。
- 内容の理解が深まる
- 精読、速読の目星をつけられる
- 記憶に定着する
「同じ本を2回も読むと読書時間が増えてしまうのでは?」
と思いますよね。
じつは、1回だけじっくり読むよりも、この方法で2回読むほうが内容の理解が深まるため、結果的に速く読めます。
本全体の「地図」を作り、「ゴール」を決める、と表現されることが多いです。
目的地に向かうとき、地図と経路を見ながら進むと迷いませんよね。
そんなイメージです。
2回目に読むときは、重要な部分はじっくり、そうでない部分は斜め読みで進めると時間を短縮できます。
また、複数回読むため、記憶に定着しやすいです。
勉強するときも2度、3度と繰り返し暗記をしますよね。それと同じ原理です。
このように、マクロからミクロに読み進めると、理解が深まり記憶にも定着しやすくなります。
予測読み
どんな内容が書いてあるか、予測しながら読む方法です。
この方法には次の効果があります。
- 思考力が鍛えられる
- 相手が言いたいことを読み取る力がつく
- 記憶に定着する
具体的には2つの方法があります。
①目次で各見出しのタイトルを見て、内容を予測
②ページをめくる前に、次のページの内容を予測
読書は「著者との対話」です。
本の内容を予測することは、コミュニケーションにおいて相手が何を伝えたいのか、を把握することにも応用できます。
また、予測が合っているか、まちがっているかの答え合わせをすることで、ただ読むよりも記憶に定着するメリットもあります。
ツッコミ読み
著者の主張や根拠について、「なんで?」「面白い!」などツッコミを入れながら読む方法です。
この方法には次の効果があります。
- 記憶に定着する
- 情報から知識に変わる
記憶に残る理由は、感情をのせて読むからです。
文章で読んだ内容より、人と会話した内容のほうが長く記憶に残りますよね。
これは、人との会話には感情がのっているからです。
本も感情的に読んでいくと、記憶に定着しやすくなります。
「すごい!」「なるほど!」だけでもメモしておくと、印象に残りますよ。
情報から知識に変わる理由は、ある事象に対し疑問を持つからです。
疑問を持ち、答えとつなぎ合わせることで、ただの情報から知識に変わります。
「なんで?」「本当に?」などツッコミを入れて、答えを探しましょう。本の中に答えがなければ、ネットで調べるのもアリです。
このようにして、日常や仕事で使える知識を増やしていきましょう。
要約読み
ことばの通り、読んだ内容を要約していく方法です。
この方法には次の効果があります。
- 内容の理解が深まる
- 記憶に定着する
- 著者の主張をつかめる
- 端的に伝える力がつく
1つの見出しごとに、どんな内容だったかを自分のことばで端的にまとめて読み進めていきます。
人に説明すると自分の復習にもなって理解度が深まる、なんて言いますよね。
それと同じで、人に説明するつもりで要約していくと理解が深まります。
また、インプットした直後に思い出そうとすると、脳が重要な情報だと認識し、記憶に定着します。
要約したメモを見返すと、著者が伝えたいことが見えてきますよ!
本の内容を端的に説明できるということは、内容を深く理解しているということです。
読書の時間が無駄にならないよう、要約する習慣をつけましょう。
まとめ
ここまで、読書術の本おすすめ8冊と、一生使える読書術5つについて解説してきました。
簡単にまとめると、読書術のベースとなるのは以下の5つ。
- 想定読み
- マクロからミクロ
- 予測読み
- ツッコミ読み
- 要約読み
この5つを実践して読書に慣れてきたら、今回ご紹介した本を参考に、ご自身にあった読書スタイルを確立していくとよいでしょう。
大事なことは、読書を楽しみ習慣化することです。
疲れているときは手を抜きつつ、無理のないペースで読書を楽しみましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本をたくさん読むならKindle Unlimitedがおすすめです。
月額980円で200万冊以上の本が読み放題!
月に3冊以上読めばもとが取れます。
最初の30日間の無料体験 & いつでもキャンセル可能
ぜひ試してみてください。